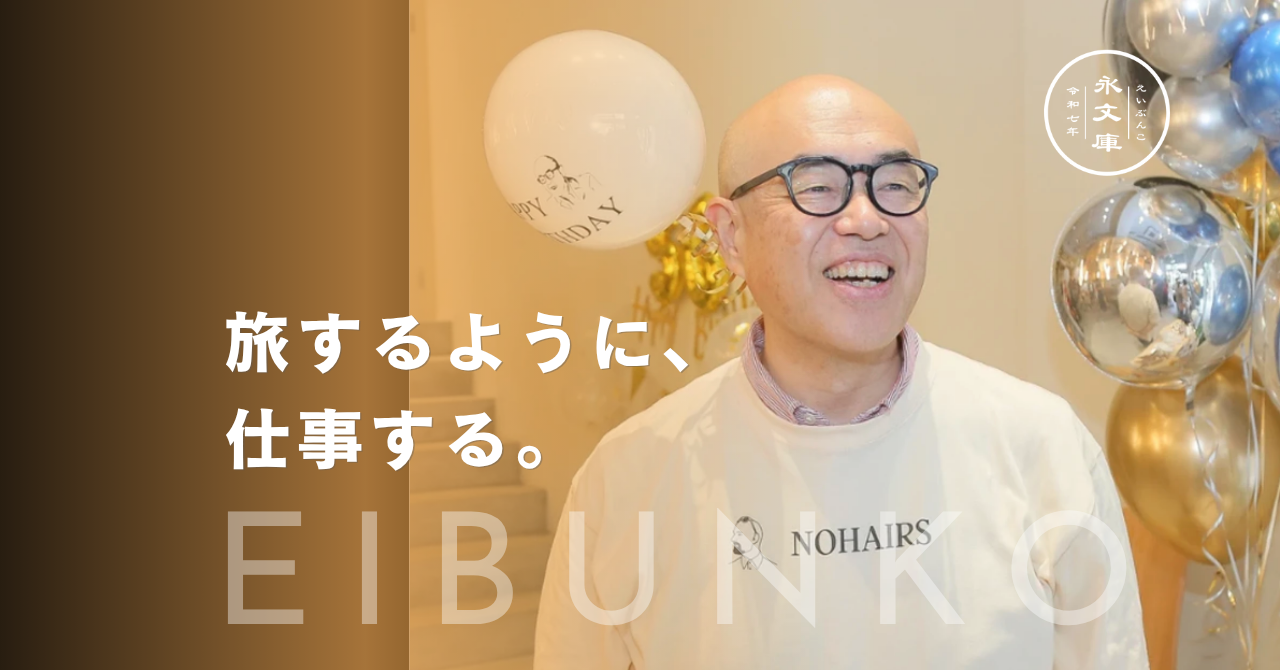「また今日から仕事か……」
そんな気分で月曜日を迎える人は、少なくないかもしれません。
でも、もしその一日が「旅行中の一コマ」だったとしたら?
アクシデントも、トラブルも、遅延や道迷いも、旅行中なら全部“ネタ”になる。
「仕事を旅行のように捉えることができたら、人生は途端に面白くなる」
そう語るのは、代表世話人株式会社 代表取締役の杉浦佳浩さん。
年間1000名以上の経営者と、紹介のみで会い続けているお方。その相手は、大企業、地方の中堅企業、金融機関はもちろんのこと一流のゲームクリエイターやテレビプロデューサー、元大物官僚、そして10代の若者まで—実に幅広いから驚きです。
あらゆる分野の人々と交わりながら、新しい価値を生み出し続けている杉浦さんに「どうすれば杉浦さんのように、仕事を楽しむことができるのか」その秘訣を聞いてみました。
読み終わる頃には、月曜日が今よりちょっとだけ、楽しみに思えてくるかもしれません。

新卒10日で退職願を。「旅行だと思ったら?」がすべての始まり
有り難いことに、「杉浦さんって毎日楽しそうですね」とよく言ってもらえるんです。でもその原点は、新卒時代の上司からのとある一言。
大学卒業後、証券会社に入社した僕は、鹿児島支店の営業に配属されました。
でも、どうも営業がうまくいかない。「自分には向いてないかもしれない」と思い、入社早々に上司に「もう退職したいです」と伝えました。
そのとき、上司が言ってくれたんです。
「じゃあ、仕事してるんじゃなくて、旅行に来てるくらいの感覚でやってみたらどう?」って。
もともと旅は好きでした。学生の頃はバックパッカーで海外を巡っていましたし、危ない目にもたくさん遭ったけれど、それも含めて全てが楽しかった。
だからその上司の言葉が、ストンと腑に落ちたんです。
「ああ、そうか。旅行中やと思えばええんや」
トラブルも、アクシデントも、失敗も、ぜんぶネタになる。電車が遅れたり、行き先が変わったり、お客さんに怒られたりしても、「まあ、旅行中やしな」と思えたら、ちょっと面白くなってくる。
最初のうちは、自分に言い聞かせるようにしていたけれど、だんだんそれが自然になっていって。気づけばもう40年以上経ちますが、今も僕は「旅行中」なんですよね(笑)
だから毎日が楽しい。
あのとき、あの言葉をくれた上司には今でも感謝しています。
うまくいくことばかりじゃない。でも、何が起きても、それを受け入れるかどうか。それだけだと思うんです。

100年前は「生きること=働くこと」だった
最近思うことがあります。
「仕事は苦しい。だからその分、プライベートを楽しむ」
そんな現代の考え方って、少し不自然じゃないかなと。
今から100年、150年前の当時の日本では、ほとんどの人が農業をして暮らしていました。「今日は疲れたから働くのはやめておこう」なんて言っていたら、生きていけなかった時代です。
だから当時は、働くこと=生きることだった。
働くことが、生きることそのものであり、それが当たり前でした。
それがいつの間にか、「仕事はつらいもの」「給料は我慢料」なんて考え方に変わってしまった。でも、そんな価値観が広まったのって、ここ100年くらいのことです。
100年というと長く感じるかもしれませんが、人類の長い歴史から見ればほんの一瞬。
たった100年で、人間の根っこが変わるはずがないですよね。
だからきっと、これから先の100年で、また元に戻っていくんじゃないかと思うんです。
昔のような、「生きること=働くこと」という感覚に。
働くというのは、人が生きている証そのものですから、それを嫌ってしまったら、人生がしんどくなるのは当たり前です。
「なんでこんなに働かされなあかんねん」ではなくて 、「働けるって有り難いな」「今日もたくさん動けたな」と思えるほうが、ずっと気持ちは楽ですし、僕は、そういう生き方のほうが好きですね。

「遠い類比」という言葉に全て詰まっている
日々多くの方とお会いして、人をお繋ぎしたり、意見を求められた場合には「こうしたらいいかもしれませんね」と、僭越ながらアドバイスをさせてもらったりすることがあります。
そんなときによく言われるんです。
「杉浦さんって、よくそんな発想出てきますね」
「どうやってそんなアイデア思いつくんですか?」
と。
実はその根っこにあるのは、「遠い類比」。AIが発展してきた今、「人間ができることって“リアルな遠い類比”しかないのでは?」とすら思っています。
アメリカに「1兆ドルコーチ」と呼ばれる伝説的な人物がいて、GoogleやApple、Facebook、Amazonといった企業の創業者たちにアドバイスをしていたのですが、
その人が口酸っぱく言っていたのが、
「目の前の事業ばかりに集中するな。遠くにあるものに触れろ」
「一見無関係に見える話や世界からしか、企業の爆発的な成長は生まれない」
ということでした。この考え方を『ファーアナロジー』と言うのですが、直訳すれば遠い類比。
僕はその話を聞いたときに「自分がこれまで思っていたことが、まさにこの言葉に集約されている」と思いました。
実際僕も30代を過ぎた頃から、社外の人と積極的に関わるようにしてきました。いわゆる「社外上司」という考え方ですね。
社内のことをちゃんと理解したうえで、社外の人とどう関わるか。でもそれって結局、「遠い類比」なんですよ。
たとえば、先日、テレビ業界の有名番組を多く手掛けたプロデューサーの方と、これまた全世界で有名なゲームを開発されたゲームクリエイターの方をお繋ぎしました。
ゲームクリエイターの方は、ユーザーを楽しませることを徹底してきた人。一方でテレビのプロデューサーの方は、視聴者だけじゃなく、スポンサーも、現場も、会社も喜ばせなければならない。ものすごい数の利害関係者を説得しながら、番組という“世界”をつくる人。
そういう“違うもの同士”が交わったとき、「あれ? これとこれ、なんか一緒にできるんちゃうか?」と自分の中の景色がパッと開ける瞬間がある。
現場で培われた深い知恵や知見というものが掛け合わさったとき、何か面白いことが起きるタイミングがあるんです。
僕がいま、業界も年齢もバラバラな、10代から80代までの方々に囲まれて仕事ができているのも、きっとみんな、「杉浦さんといたら、なんかおもしろいことが起きそう」と思ってくれてるからなんだと思うんです。
それが「遠い類比」の力だと思っています。

社外上司がくれた、視野の広がり
先ほど少し触れましたが、僕は「社外上司を持つ」ということを意識してきました。
特に30歳を過ぎてからは、社内のことだけでなく、社外とどう付き合っていくかがとても大事になってくると実感しています。
でもこれ、急に思いついたわけじゃないんです。
きっかけは、前職の損保会社にいたときのことでした。会社にはほぼ変化が少なく、多くの人が「自分の担当業務」だけを見ている状態。
そうなると、視野がどんどん狭くなってしまう上に、そのことにすら気づかずに働いている人もたくさんいました。
この状況は、その前に働いていたキーエンスとはまったく逆でした。
キーエンスでは、社内にいるだけで次々と課題がやってきて、日々新しいことに取り組む環境がありました。だから、社外に出る必要なんてほとんどなかったんです。
でも、その後働いた損保会社では違った。
社外に出なければ、何も起きない。
「このままやったら自分がだめになってしまう。自分の仕事をきちんと終わらせたら、積極的に外に出て人と会おう」
そう思って、意識的に社外に出るようになりました。
中でも意識していたのは、視野の広い人たちと会うことでした。
そうすると、自分の仕事の仕方もまるっきり変わってくる。
誰と出会うかで、自分の見えている景色も、言葉も、行動もすべてが変わることを実感しました。
そういう意味で、前職の損保会社での経験には今でも感謝しています。あれがなかったら、今の自分は確実にいませんから。
「社外上司」というのは、外から仕事を評価してくれる人、というだけではなくて、
僕にとっては、“生き方を見せてくれる人”です。

20年以上のお付き合いになる方々も多いですが、未だに学ばせてもらっています。
昨日も、日本の歴史的な有名政治家の官僚側で秘書されていた方から、メッセージが届きました。そこには「杉浦ちゃん、有り難う」と書かれてあって。ああ、僕はこうした方々にずっと育ててきていただいたんだな、有り難いなと、改めて思いました。
視野が広い人というのは、自分の仕事や会社のことだけを考えているわけではなく、人との関係も深く大切にされている方が多い。逆に、視野が狭い人は、どれだけ一生懸命働いても、自分のことしか考えていないので、自分の殻を破れない。
僕はそれを、身をもって実感しているからこそ、今も「誰とお会いするか」をものすごく大事にしているんです。
できるだけ長く続けたい
「杉浦さんの目標はなんですか?」
たまに、そう聞かれることがよくあります。
そのとき、僕はこう答えています。
「今やっていることを、できるだけ長く続けたいです」と。
長生きしたい、という意味ではありません。この「旅みたいな、ありがたい毎日」を、できるだけ長く――できれば死ぬ直前まで味わっていたい。
「今日もまた仕事か…」という気持ちで始まる一日と 、「今日はどんなおもろいことが起こるんやろ?」という気持ちでスタートする一日とでは、見える景色がまるで違ってきますから。
そういえば、会社員時代にこんなことがありました。毎朝通勤のときに、道ばたで「ありがとう、ありがとう」って声に出して歩いていたんです。
ある意味、自分なりの訓練ですね。
するとある日、鳩が寄ってきたり、スズメがずっと横を飛んでついてきたりして。餌なんてあげてないのに(笑)
「人と動物って、こんなに仲良くなれるもんなんやなあ」と思いましたね。
ほんとに、すべては考え方ひとつ。
もし僕が沈んだ顔でつまらなさそうにしていたら、きっと誰も寄ってきて下さらない。でも、「杉浦さんってなんか楽しそう」「なんかようわからんけど面白そう」って思ってもらえるから、人が寄ってきて下さるんだと思います。
それだけのことです。

よく話すたとえがあるんです。映画『フォレスト・ガンプ』のワンシーン。
ガンプが、ただ黙って走り続けるシーンがありますよね。
何の説明もしていないのに、周りの人たちは「この人はきっと何か意味のあることをしているに違いない」と思って、気づけばどんどん後ろに人がついてくる。
あれを見て、「ああ、まさにこれやな」と思ったんです。
何も言わなくても、一生懸命、楽しそうにやっていたら、人は自然とついてきてくれる。
だから、僕はこれからも走り続けます。
この旅は、まだまだ終わらない。
楽しい毎日に、本当に感謝です。
編集後記
「仕事を旅行のように捉える」
その考え方が、これほどリアルに伝わってくる方は杉浦さんが初めてでした。
怒られても、予定通りにいかなくても、電車に乗り遅れても。
それを旅のハプニングとして笑い飛ばし、次の景色にワクワクしながら進んでいく。誰よりも人生を面白がり、誰よりも他人を応援し、誰よりも「ありがとう」を惜しまない。
杉浦さんのまわりに人が集まる理由は、人生という“旅を楽しむ力”にあることを、改めて感じさせられました。
さあ、今日はどんな出会いがあるだろう。
どんな偶然があるだろう。
月曜日の朝が、ほんの少しだけ楽しみになる。
そんな旅の始まりに、背中をそっと押してくれるような、そんな時間。
杉浦さん、本当にありがとうございました。